
学科紹介(2014年以降入学生) |
|||||||||
|
【学科概要】 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、災害からの復興に対する貢献、地震・津波避難施設の各地域での在り方など建築学が果たすべき新たな課題も現出しています。これらは、加速する高齢化社会への対応とともに北海道内においては、冬期災害時の対応も含めた検討が重要となっています。また、電力需給の関係からは、より一層の省エネルギー、省資源化も建築学に求められる重要な課題となっています。 建築学科では、積雪寒冷地固有の問題も含めた建築学の各分野の基礎知識を修得したうえで、新たな課題も含めた近年の建築分野で進む急速な専門化への対応と、地域環境から地球環境までを視野に入れた循環型を目指す多様な社会の要請に応えるための能力を培うことを教育研究上の目的としています。 【教育目的】 建築学科では、社会生活を送るうえで必要となる知識・理解、汎用的技能、態度・志向性、創造的思考力、の修得のもとに、建築に関する総合的な知識技術を基盤として、専門性を高めたカリキュラムで積雪寒冷地固有の問題も含めた建築計画手法や建築技術を習得し、地域社会に貢献する次のような建築設計者・建築技術者を養成します。 ①風土、歴史、文化などを踏まえた建築や都市空間をデザインする創造力と設計能力を有する建築設計者 ②健康で快適な生活環境や環境負荷の小さな建築空間を創るための建築環境・設備技術者 ③建築空間の構造的安全性、耐久性、信頼性を創出するための建築構造・施工技術全般の専門知識と設計技術を習得した建築設計者、技術者 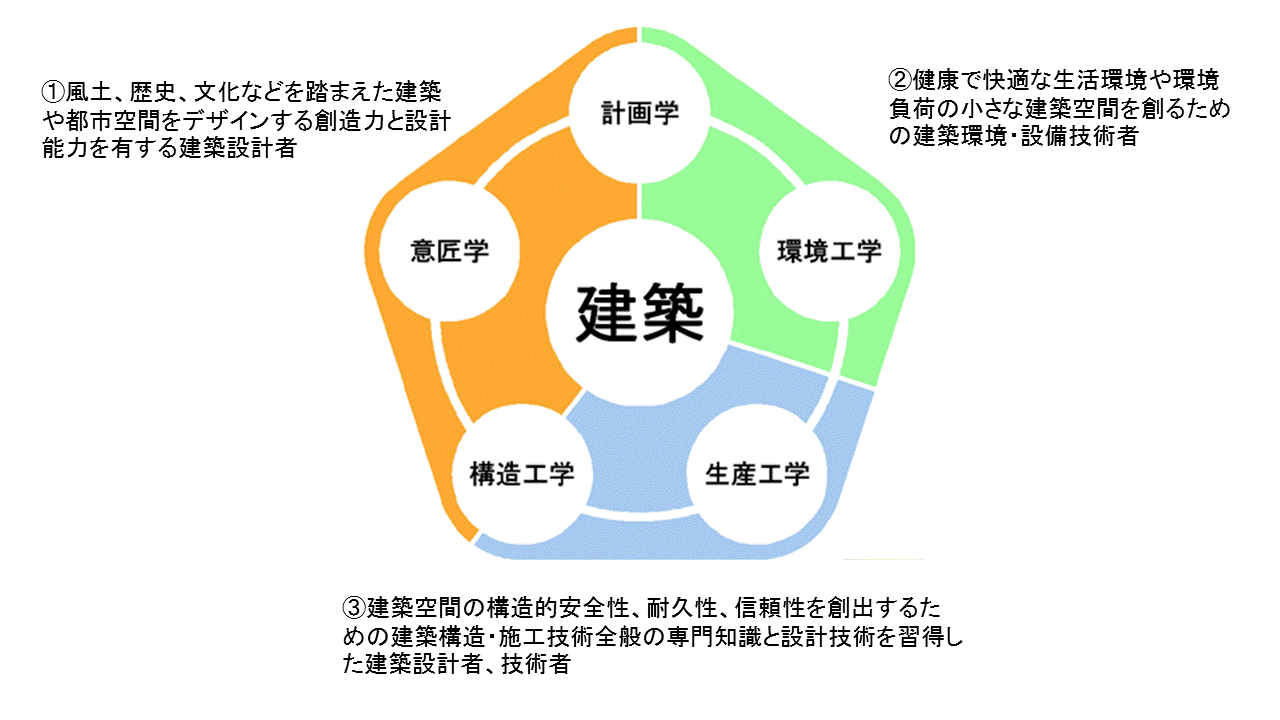 【学科のカリキュラム】 近年、建築の専門化が急激に進み、多様な社会のニーズに応える必要が生じています。本学建築学科はその要求に応えるべく、建築の各専門分野の基礎的知識の充実とともに、学生個々の適性に応じたより専門性の高い教育が受けられるカリキュラムになっています。また、多くの卒業生の協力を得て、施工現場や鉄骨工場あるいはモデルハウスの見学研修を行い、現場で建築と向き合う重要性を学ぶとともに、協同作業を伴う講義・演習も多く取り入れ、将来社会人として活躍するための不可欠な教養や能力を身に付けることができるよう配慮した構成になっています。 建築学科では設計演習科目を基本軸に置いており、設計演習科目として1年後期から3年後期までの2年半を通じてカリキュラムに計画しています。設計演習科目は、これから学ぶ様々な専門知識を具体的な建築の設計を通じて、建築物に具現化する最も重要な科目となっています。 本学は北海道という寒冷積雪地に設立されています。わが国の文化は温暖地方に発達したもので、古来の建築技術は寒冷地に適したものではありませんでした。積雪寒冷地に適した建築、すなわち「寒地建築」が問題になったのは、約50年前からです。建築学科は、北海道という地域に根ざした大学として、寒地建築設計、建築と省エネルギー、寒地における鉄骨造の設計と施工、雪が建築に及ぼす影響等に関するユニークな講義・演習内容を用意しています。 【学科の沿革】
|
|||||||||
| 取得を目指せる資格と、主な就職先の紹介はこちら 本学建築学科の教員の紹介はこちら | |||||||||
Copyright (C) 2014, Department of Architecture,Hokkaido University of Science |